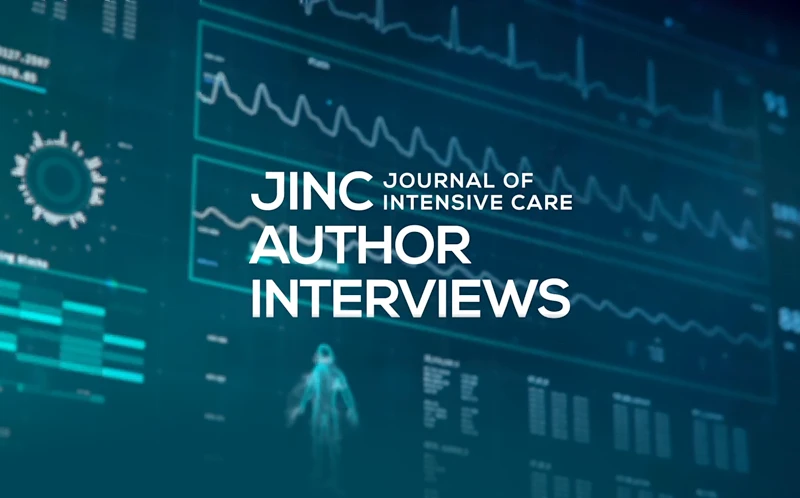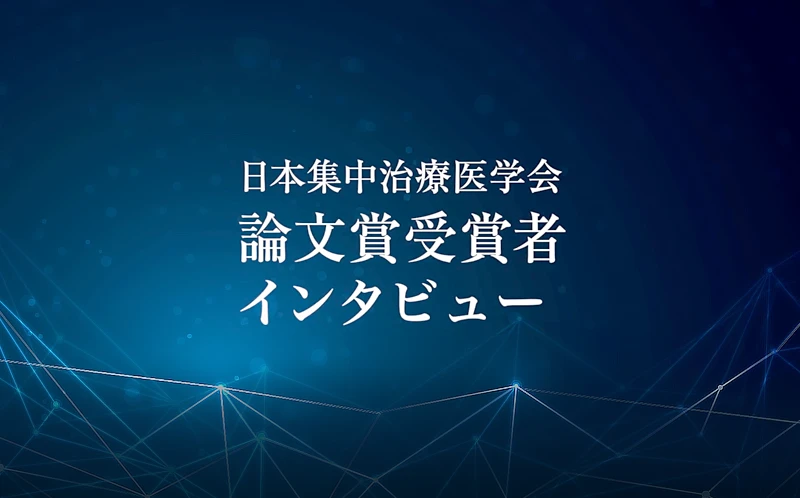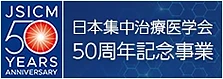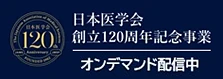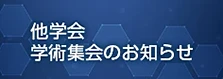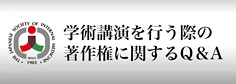U35月例報告 2025年7月
2025年7月
■Topics
第38回日本小児救急医学会学術集会・第32回小児集中治療ワークショップ
U35コンシェルジュブース報告
U35コンシェルジュブース報告
報告者:奥脇 一 開催日:2025年7月5日~6日
第38回日本小児救急医学会学術集会・第32回小児集中治療ワークショップは初の合同開催であり、小児の急性期医療にかかわる多くの医療者が参加した盛大な学術集会となりました。この貴重な機会に、若手医療者に対して、集中治療領域における各職種のキャリアパスや専門認定資格の内容、学術集会の周り方などについてU35プロジェクトメンバーに相談できる場所としてコンシェルジュブースを実施しました。
学会期間は3日間でしたが、その中の2025年7月5日、6日の両日13時~16時、担当を分担してブースを運営し、2日で合計11名の方にお越しいただきました。(参加者内訳:医師3 名、看護師3名、医学生3名、看護学生2名)
参加者からは、キャリア・認定・専門資格に関する質問、U35の活動や入会に関する質問をいただき、またU35メンバーの交流もでき有意義なブースとなりました。また、学生の参加者との交流が私たちにとっても新たな刺激となり、企画にも好影響を与えました。小児集中治療分野においても多職種・横のつながりはとても重要なものであり、今後もU35 の宣伝、学会加入、同世代の多職種のつながりといった活動を続けていきます。
学会期間は3日間でしたが、その中の2025年7月5日、6日の両日13時~16時、担当を分担してブースを運営し、2日で合計11名の方にお越しいただきました。(参加者内訳:医師3 名、看護師3名、医学生3名、看護学生2名)
参加者からは、キャリア・認定・専門資格に関する質問、U35の活動や入会に関する質問をいただき、またU35メンバーの交流もでき有意義なブースとなりました。また、学生の参加者との交流が私たちにとっても新たな刺激となり、企画にも好影響を与えました。小児集中治療分野においても多職種・横のつながりはとても重要なものであり、今後もU35 の宣伝、学会加入、同世代の多職種のつながりといった活動を続けていきます。

日本集中治療医学会 第9回関東甲信越支部学術集会
報告者:三森 薫
開催日:2025年7月26日
本報告の目的は、日本集中治療医学会第9回関東甲信越支部学術集会におけるU35メンバーの関わりを振り返り、若手(ここでは「U35」世代)の視点から得られた学びを共有し、今後の活動の一助とすることです。
2025年7月26日、横浜市立みなと赤十字病院の武居哲洋先生を会長として支部会が開催されました。本支部はこれまで会員数に比して参加者数の伸び悩みが課題でしたが、今回は世代や職種をこえた参画を促す工夫がなされ、過去最高となる965名が参加しました。背景には、プログラム委員長を務めたU35卒業生・鈴木健人(すずき たけと)さん(U35のルールに習いあえて「さん付」)の呼びかけに応じ、多くの若手がプログラムコアメンバー、ワーキンググループ、演者、座長として協力したことがあります。学会運営にU35が組織として関与したわけではありませんが、このネットワークが生かされた一例として記録いたします。
U35メンバーが関わったプログラムを三つ紹介します。第一に、臨床倫理カンファレンスの実演です。これは総会のU35企画を発展させたもので、参加者が実践的議論を体験できる場となりました。第二に、架空のECMO症例を題材とした多職種・施設横断的な討論です。医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士からなるチームが立場を超えて意見を交わし、多角的な視点が示されました。第三に、研究に関する若手・多職種による議論です。従来は医師主導となりがちな研究について、医師以外の職種でも主体的に取り組める可能性や、日常臨床との両立の工夫など、具体的課題に寄り添ったことで、聴講者も交え活発な意見交換がされました。一方で、アイディアを具体化する過程において、聴講者像の明確化や実行可能性の評価、論点の取捨選択をテンポよく進める力、いわば「具現化力」の不足という課題が浮かび上がりました。しかしながら、いずれの企画も参加者同士の相互作用と相乗効果を生み出し、支部会の特色を高めるものとなりました。今後は年度ごとに完結せず、継続的につながる企画を築ければより魅力が高まると感じました。
今回の支部会は、会長を務められた武居先生が目指された「文化祭」のイメージそのものでした。異なる背景(クラスや学年や学校=職種や世代や施設)を越えて声を掛け合い、一つの企画を作り上げる体験は、大人になってからの学祭といえる貴重な財産となりました。U35メンバーが担ったのは運営の一部にすぎませんが、その営みの一端に関わることで、準備にかけた熱量や終えた後の達成感を共体験し、幸運にもその喜びを分かち合うことができました。改めて、会長、学会理事長をはじめ諸先輩方に、新しい提案を寛容に受け入れ、昇華へ導いていただいたことに御礼申し上げます。
今後も私たちU35は、学会活性化に向け世代や職種の垣根を超える原動力であれるよう活動していきます。このような有難い機会に出会えるU35に関心を持たれた方は、ぜひ私たちと共に歩んでいただければ幸いです。
詳細な学術集会の内容は別途、大会長からの報告書をご参照ください(→リンク https://www.jsicm.org/meeting/report/kanto-koshinetsu9.html、当支部会だけでなく他支部会の報告書もぜひご覧ください)。
2025年7月26日、横浜市立みなと赤十字病院の武居哲洋先生を会長として支部会が開催されました。本支部はこれまで会員数に比して参加者数の伸び悩みが課題でしたが、今回は世代や職種をこえた参画を促す工夫がなされ、過去最高となる965名が参加しました。背景には、プログラム委員長を務めたU35卒業生・鈴木健人(すずき たけと)さん(U35のルールに習いあえて「さん付」)の呼びかけに応じ、多くの若手がプログラムコアメンバー、ワーキンググループ、演者、座長として協力したことがあります。学会運営にU35が組織として関与したわけではありませんが、このネットワークが生かされた一例として記録いたします。
U35メンバーが関わったプログラムを三つ紹介します。第一に、臨床倫理カンファレンスの実演です。これは総会のU35企画を発展させたもので、参加者が実践的議論を体験できる場となりました。第二に、架空のECMO症例を題材とした多職種・施設横断的な討論です。医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士からなるチームが立場を超えて意見を交わし、多角的な視点が示されました。第三に、研究に関する若手・多職種による議論です。従来は医師主導となりがちな研究について、医師以外の職種でも主体的に取り組める可能性や、日常臨床との両立の工夫など、具体的課題に寄り添ったことで、聴講者も交え活発な意見交換がされました。一方で、アイディアを具体化する過程において、聴講者像の明確化や実行可能性の評価、論点の取捨選択をテンポよく進める力、いわば「具現化力」の不足という課題が浮かび上がりました。しかしながら、いずれの企画も参加者同士の相互作用と相乗効果を生み出し、支部会の特色を高めるものとなりました。今後は年度ごとに完結せず、継続的につながる企画を築ければより魅力が高まると感じました。
今回の支部会は、会長を務められた武居先生が目指された「文化祭」のイメージそのものでした。異なる背景(クラスや学年や学校=職種や世代や施設)を越えて声を掛け合い、一つの企画を作り上げる体験は、大人になってからの学祭といえる貴重な財産となりました。U35メンバーが担ったのは運営の一部にすぎませんが、その営みの一端に関わることで、準備にかけた熱量や終えた後の達成感を共体験し、幸運にもその喜びを分かち合うことができました。改めて、会長、学会理事長をはじめ諸先輩方に、新しい提案を寛容に受け入れ、昇華へ導いていただいたことに御礼申し上げます。
今後も私たちU35は、学会活性化に向け世代や職種の垣根を超える原動力であれるよう活動していきます。このような有難い機会に出会えるU35に関心を持たれた方は、ぜひ私たちと共に歩んでいただければ幸いです。
詳細な学術集会の内容は別途、大会長からの報告書をご参照ください(→リンク https://www.jsicm.org/meeting/report/kanto-koshinetsu9.html、当支部会だけでなく他支部会の報告書もぜひご覧ください)。
■座談会報告
第27回緩和ケア座談会
報告者:吉澤 和大
開催日:2025年7月16日
今回の緩和ケア座談会では、少しICUを飛び出して「救急隊とDNAR」をテーマにスモールグループでのディスカッションをしました。今回は救急隊向けにDNARの講演をした先生や、救急救命士を配偶者にもつ先生にも参加いただき、ICUと救急外来両方を見ている医師・看護師を中心に集まって、現状の課題やどんな解決策がありそうかディスカッションをしました。
課題としては、救急隊のコミュニケーション、DNARでの不搬送が可能な地域のルールやその浸透具合、二次救急と三次救急の板挟みになる救急隊、かかりつけ医とどれくらいACPが進んでいるかなどが挙げられました。救命救急センターとしては、訪問診療クリニックとの連携を強めたり、救急隊とのフィードバックを行なったりすること、病院の方から急変時カードを用意してスムーズに救急隊と病院が連携を取れるようにすること、そこに心停止時DNARといった内容を加えてゆくゆくはPOLSTと呼べるような医師による事前指示書の形にしていくことができればよいのではないかといった意見が出てきました。そして、最終的には、病院とかかりつけ医と患者本人・家族とが連携してACPを進めていくことで、救急要請ではなくかかりつけ医への相談が増えたり、いざ救急隊の前で心停止になった際も落ち着いてかかりつけ医と連携してDNARのプロトコルに繋げたりすることができるのではないか、そしてICUも擁する救命救急センターとしては現場判断を尊重して、なるべく依頼があったら受け入れられるよう体制づくりをしていくべきといった結論につながりました。次回は、ここから派生してACPへの議論に繋げていきたいと思います。
課題としては、救急隊のコミュニケーション、DNARでの不搬送が可能な地域のルールやその浸透具合、二次救急と三次救急の板挟みになる救急隊、かかりつけ医とどれくらいACPが進んでいるかなどが挙げられました。救命救急センターとしては、訪問診療クリニックとの連携を強めたり、救急隊とのフィードバックを行なったりすること、病院の方から急変時カードを用意してスムーズに救急隊と病院が連携を取れるようにすること、そこに心停止時DNARといった内容を加えてゆくゆくはPOLSTと呼べるような医師による事前指示書の形にしていくことができればよいのではないかといった意見が出てきました。そして、最終的には、病院とかかりつけ医と患者本人・家族とが連携してACPを進めていくことで、救急要請ではなくかかりつけ医への相談が増えたり、いざ救急隊の前で心停止になった際も落ち着いてかかりつけ医と連携してDNARのプロトコルに繋げたりすることができるのではないか、そしてICUも擁する救命救急センターとしては現場判断を尊重して、なるべく依頼があったら受け入れられるよう体制づくりをしていくべきといった結論につながりました。次回は、ここから派生してACPへの議論に繋げていきたいと思います。
U35 Nursing Journal Club
報告者:筒井 梓
開催日:2025年7月29日
前回の看護師座談会に引き続き、今回もNursing Journal Clubを開催しました。今回は、名古屋大学大学院の正木さんに、ICU の環境に関する論文を紹介していただき、みなさんの自施設の紹介や比較、理想とするICUはどんな環境かを話し合いました。
紹介していただいた論文は、患者スペースに限らず、スタッフスペースにまで言及しており、みなさんとの話し合いもさまざまな切り口で行うことができました。論文の中では取り上げられていませんでしたが、今回参加のみなさんが共通して感じていたのは、人工呼吸器やECMOなどと同乗しても、十分なスペースがあるエレベーターが欲しいという点で、話が盛り上がりました。
各メンバーの ICU との比較に話が及ぶと、全部屋スケールベッドでエアマットレスと人工呼吸器が設置してあるICU もあれば、最低限の物品だけで運営をしているICU もあり、「羨ましい」という声や「衝撃的...」という感想があり、自施設のICU 環境を俯瞰してみる機会となりました。こうした他施設のことを知れる機会があるのも、U35 の強みであると思うので、今後もこのようなテーマでトークをしていきたいと思います。
紹介していただいた論文は、患者スペースに限らず、スタッフスペースにまで言及しており、みなさんとの話し合いもさまざまな切り口で行うことができました。論文の中では取り上げられていませんでしたが、今回参加のみなさんが共通して感じていたのは、人工呼吸器やECMOなどと同乗しても、十分なスペースがあるエレベーターが欲しいという点で、話が盛り上がりました。
各メンバーの ICU との比較に話が及ぶと、全部屋スケールベッドでエアマットレスと人工呼吸器が設置してあるICU もあれば、最低限の物品だけで運営をしているICU もあり、「羨ましい」という声や「衝撃的...」という感想があり、自施設のICU 環境を俯瞰してみる機会となりました。こうした他施設のことを知れる機会があるのも、U35 の強みであると思うので、今後もこのようなテーマでトークをしていきたいと思います。
2025年度第2回おくすり座談会 臨床工学技士×薬剤師 コラボ
テーマ:「人工呼吸器管理中の吸入療法ってどうしていますか?」
報告者:松本 美緒
開催日:2025年7月29日
今回は、臨床工学技士(CE)と薬剤師を中心に、医師なども交えた多職種による座談会を開催し、「人工呼吸器管理中の吸入療法ってどうしていますか?」をテーマに意見交換を行いました。薬剤師・CEがそれぞれ事前に準備していた質問をもとに、活発な議論が展開されました。
座談会では双方向の質疑応答が行われ、薬剤師に対しては「去痰薬のpMDIが少ない理由」「吸入と内服の効果の違い」「薬剤情報の収集方法」など、CEに対しては「非同調時における吸入薬の効果」「吸入薬の使用感や効果の印象」「気管切開患者への吸入方法」などの問いが挙げられ、それぞれの専門性を活かした実践的な議論が行われました。
また、各施設における薬剤師とCEの連携のあり方や、実臨床での距離感についても話題となりました。現時点では、薬剤師とCEが密接に連携している施設は限られているものの、人工呼吸器管理中の吸入療法においては、両者が関与することで治療の質をより高められるという共通認識を得ることができました。
今後は、自施設においても薬剤師とCEが積極的に連携し、より良い医療の提供を目指してまいりたいと考えております。
座談会では双方向の質疑応答が行われ、薬剤師に対しては「去痰薬のpMDIが少ない理由」「吸入と内服の効果の違い」「薬剤情報の収集方法」など、CEに対しては「非同調時における吸入薬の効果」「吸入薬の使用感や効果の印象」「気管切開患者への吸入方法」などの問いが挙げられ、それぞれの専門性を活かした実践的な議論が行われました。
また、各施設における薬剤師とCEの連携のあり方や、実臨床での距離感についても話題となりました。現時点では、薬剤師とCEが密接に連携している施設は限られているものの、人工呼吸器管理中の吸入療法においては、両者が関与することで治療の質をより高められるという共通認識を得ることができました。
今後は、自施設においても薬剤師とCEが積極的に連携し、より良い医療の提供を目指してまいりたいと考えております。
発行者:U35プロジェクト運営委員会